こんにちは!「楽しく学ぶ家庭学習|おうちスタディ」を運営しているcocoです🌸
「8の段って、なんだか大きな数ばっかり…」「やっと6の段・7の段まで来たのに、また難しくなった…」
そんなふうに感じるお子さんも多いかもしれません。
でも大丈夫です☺️
わが家でもつまずくことはありましたが、“できた!”の瞬間をいっしょに喜ぶ家庭学習を積み重ねていくうちに、少しずつ前に進むことができました。
今回は【九九シリーズ】第7回として、「8の段」の覚え方やリズム、苦手ポイントを乗り越える工夫をご紹介します。
親子で“ちょっとがんばってみようかな”と思えるヒントをたくさん詰めこみましたので、ぜひご家庭での学び時間にお役立てくださいね🍀
■ 8の段が難しい理由
- 答えが大きく、数字のイメージがつかみにくい
- 「48」「56」「64」などが並び、混乱しやすい
- 7の段と混同してしまうことが多い
でも、実は規則性の多い段なので、「コツ」をつかむと一気に覚えやすくなるのも8の段の特徴です。
- 偶数がずらっと並ぶ
- 末尾の数字が「8→6→4→2→0」と変化する
- 「2の段×4」「4の段×2」とも考えられる
子どもにとっては“気づく体験”が大切。「ママ、全部偶数!」と嬉しそうに教えてくれたことをよく覚えています♡
■ 7の段・8の段が混ざる練習で「ごちゃまぜミス」を防ごう!
7の段・8の段は、「数が大きくなる」「似たような数字が出てくる」ため、覚えたつもりでも混ざってしまいやすい段です。
とくに間違えやすいのが…
- 7×8=56と8×7=56
- 7×9=63と8×8=64
こんなときは「ごちゃまぜ練習」でミスを防ぎましょう!
✅ 例:「7×6→8×3→7×8→8×6→7×9→8×7」
✅ カードや音読練習で、順番をあえてバラバラにしてみる
慣れてきた段こそ、混乱しやすい。
ごちゃまぜ練習で、「しっかり覚えているかどうか」を確認していきましょう!
■ わが家で実践した「8の段」を楽しく覚える方法
① お風呂学習でリラックスしながら暗唱
壁に貼ってある九九表を見ながら、まずは一度声に出して全部言ってみる。
言えなかったところだけ、表を見てすぐ確認。
子どもが言えたときは、「ここ言えたね!」「昨日より速いよ!」と小さく声かけ。
この「すぐほめる」が次の意欲につながりました☺️
② リズムで覚えるとテンポよく進む
8の段は、手拍子を入れてテンポよく読むと覚えやすくなります。
「ハチイチガ 8! ハチニ 16! ハチサン 24!」
というように、メロディ風に声に出すだけで記憶が安定します。
朝の数分や、学校に行く前のちょっとした時間におすすめです。
③ 混乱しやすい3つだけを集中練習
8の段で特につまずきやすいのは、次の3つ。
- 8×6=48
- 8×7=56
- 8×8=64
わが家では、この3つだけカードにして、1日1分だけクイズ形式で練習しました。
できた瞬間に「ヤッタね!」とハイタッチをしてあげると、達成感がアップします✨
④ 語呂合わせで遊びながら暗記
| 式 | 語呂合わせ(子ども向け) |
|---|---|
| 8×1=8 | ハチいち「やっぱり8」 |
| 8×2=16 | ハチに「いろ(16)がカラフル」 |
| 8×3=24 | ハチさん「にっし(24)り笑顔」 |
| 8×4=32 | ハチよ「さんにん(32)でピクニック」 |
| 8×5=40 | ハチご「しれっと(40)成功」 |
| 8×6=48 | ハチろく「よわ(48)ないよ〜」 |
| 8×7=56 | ハチなな「ごろごろ(56)お昼寝」 |
| 8×8=64 | ハチハチ「むし(64)さん集合」 |
| 8×9=72 | ハチく(ん)「なにする?(72)」 |
大人にはちょっと強引に思える語呂合わせでも、子どもにとっては「楽しい!」「イメージしやすい!」が大切です🐝
声に出してリズムよく唱えていくうちに、自然と九九が身についていきますよ。
■ 8の段|語呂合わせ我が家ランキングTOP3
お子さんに人気だった語呂合わせを、覚えやすさ・インパクト・リズムのよさでランキングにしました♪
| 順位 | 九九の式 | 語呂合わせ | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 8×8=64 | ハチハチ「むし(64)さん集合」 | 「ハチ×ハチ」で虫のイメージがぴったり! |
| 2位 | 8×7=56 | ハチなな「ごろごろ(56)お昼寝」 | ネコ好きさんに大人気のごろごろ表現♪ |
| 3位 | 8×3=24 | ハチさん「にっし(24)り笑顔」 | 「にっしり」が楽しい響きで覚えやすい! |
このように、「ダジャレっぽさ」や「動物・もののイメージ」があると、子どもはスッと覚えやすくなります☺️
迷ったときは、ランキング上位の語呂合わせから声に出して読んでみてくださいね!
■ 九九8の段 一覧表(コピー&印刷OK)
| 式 | 答え |
|---|---|
| 8×1 | 8 |
| 8×2 | 16 |
| 8×3 | 24 |
| 8×4 | 32 |
| 8×5 | 40 |
| 8×6 | 48 |
| 8×7 | 56 |
| 8×8 | 64 |
| 8×9 | 72 |
一覧表は、プリントして冷蔵庫など目に見えるところに貼るのも効果的です。「見る・声に出す・書く」をセットで繰り返すと、記憶の定着が一気に進みます。
■ 親子で使える会話例
👩:「8×6は?」
👦:「48!」
👩:「よく覚えてるね〜😊 次はスピードアップで言ってみる?」
テンポよく明るく声かけするだけで、「やってみよう!」の気持ちが自然と育つのを感じました。
焦らず、お子さんのペースに合わせて少しずつ取り組めば大丈夫です。
おうちでの学びが“楽しい時間”になりますように☺️
■ まとめ:8の段は“できた”を積み上げるのがカギ
8の段はつまずきやすいぶん、出来たときの喜びが大きい段でもあります。
お風呂学習・リズム・語呂合わせを組み合わせながら、
お子さんのペースで「できた!」を増やしていきましょう✨
次回は、九九シリーズの最終回「9の段」!
いちばん大きい数字の段も、楽しくマスターできる工夫をお届けします🌸
💬 よくある質問Q&Aコーナー
読者の皆さまからいただいた声をもとに、よくあるお悩みをQ&A形式でご紹介します☺️
Q. 7の段・8の段で、よく間違えるのはどこ?
A. 「7×8=56」「8×7=56」など、同じ答えになる式が混ざってしまうお子さんが多いです。
カードにしてシャッフル練習をしたり、左右のリズムで体を使って覚える方法もおすすめですよ♪
Q. 語呂合わせだけで大丈夫?
A. 語呂合わせはあくまで“最初のとっかかり”です。
慣れてきたら「リズム読み」や「書いて答えるトレーニング」も組み合わせていきましょう☺️
■ 関連記事
📝 この記事で紹介した内容の出典
九九や計算の指導は、文部科学省が示す「小学校学習指導要領(算数)」でも、
反復学習や日常生活と結びつけた学びの大切さが明記されています。
最後までお読み頂きありがとうございます🌸

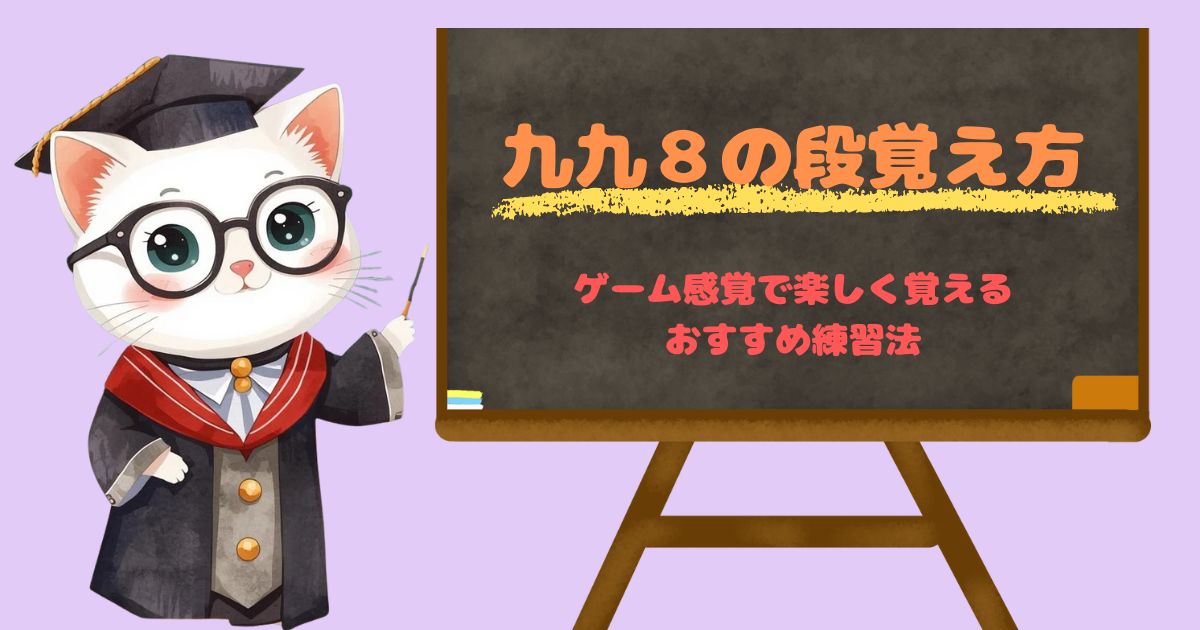


コメント