☆彡ようこそ!楽しく学ぶ家庭学習ブログへ
「楽しく学ぶ家庭学習」をテーマに、おうちでできる勉強法やおすすめアイテムを紹介しています。
「計算はできるのに文章問題になると止まる…」小学2年生によくあるつまずき
小学2年生の算数では、かけ算やひき算の導入が始まり、文章問題も一気に複雑になります。
「数字の計算はできるけれど、文章になるとわからなくなる」という子はとても多いです。
その背景には、「文章の意味を読み取る力」や「場面をイメージする力」がまだ育ちきっていないことが関係しています。
どうして文章問題でつまずくの?よくある3つの原因
① 問題文の意味が理解できていない
「だれが」「なにを」「どうした」がうまくつかめず、何を聞かれているかがわからない状態です。文章が長くなるほど混乱しやすくなります。
② 数字の使い方に迷ってしまう
「3つのりんごが入ったかごが4つある」など、2つ以上の数字が登場すると、「どれとどれを使えばいいのか?」と迷ってしまいます。
③ どの計算を使うべきか判断できない
「たすの? ひくの? かけるの?」という演算の使い分けができないと、式が立てられません。
家庭でできる!文章問題の理解を深める教え方
1. 問題文を声に出して読んでみよう
音読することで、頭の中で場面をイメージしやすくなります。親子で一緒に読むことで、理解が深まります。
2. 絵や図で「見える化」する
文章だけではイメージが難しい子には、実際に絵を描いて見せるのが効果的です。
たとえば「りんごが3つ入ったかごが4つ」→かごを4つ描いて、それぞれに3つの丸を描かせると「3×4=12」の式につながります。
3. 「だれが」「なにを」「どうした」に分けて考える
国語の読解のように、文章の構造を分解して考える練習をすると、意味を整理しやすくなります。
家庭でできる簡単な声かけの工夫
文章問題を解くときは、次のような声かけをしてみましょう:
- 「何がわかってるかな?」
- 「これはどういう場面かな?」
- 「その子は何をしたのかな?」
- 「どんな式になりそう?」
こうした問いかけを繰り返すことで、文章の構造や流れをつかむ練習になります。
簡単な文章問題の例(家庭で出せるミニ問題)
例1:
1つのかごに りんごが3つ入っています。かごが4つあると、りんごはぜんぶで何こありますか?
例2:
1本120円のえんぴつを3本買いました。ぜんぶで何円になりますか?
例3:
8こあるみかんを、2人で同じ数ずつ分けると、1人は何こずつもらえますか?
こうした日常的な内容であれば、親子で会話の中でも取り組みやすくなります。
まとめ|文章問題は「慣れ」と「言語化」で克服できる
文章問題は、単に計算が得意なだけでは解けません。「読み取る力」と「考える力」を育てることが大切です。
まずは簡単な問題から始めて、「わかった!」「できた!」という小さな成功体験を積み重ねていくことが、苦手克服への第一歩になります。
焦らず、ゆっくりと、親子で楽しく取り組んでみましょう。


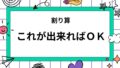

コメント